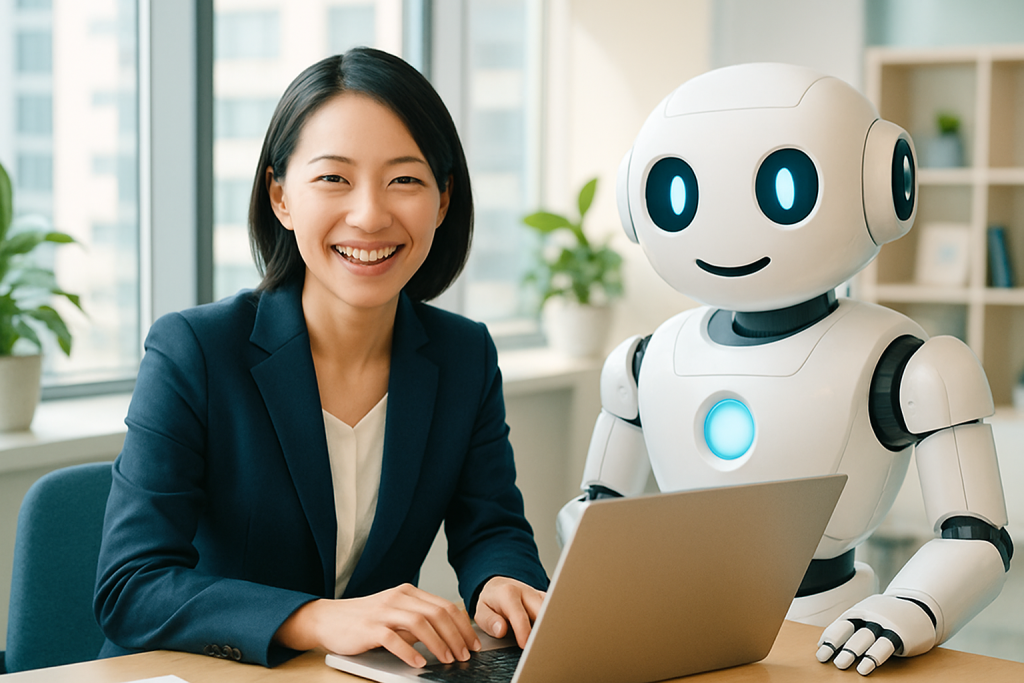
## 導入文
AI技術の急速な進化は、世界中で「雇用の未来」に関する議論を巻き起こしています。多くの先進国でAIによる仕事の自動化への懸念が高まる中、日本のビジネスパーソンは、AIによる失業に対して異例なほど楽観的であることが、日経BPの独自調査で明らかになりました。この**先進国では珍しい楽観論**の背景には、日本特有の雇用慣行や社会構造が深く関わっていると考えられます。
## 日本のAI失業懸念:世界とのギャップ
日経BPの調査によると、AIの進化によって自分の仕事がなくなってしまうことを「懸念していない」と答えた日本のビジネスパーソンは、他の先進国と比較して非常に高い割合に上りました。これは、AIに対する一般的な国際的な認識とは一線を画す結果です。
### 楽観論の背景にある日本特有の要因
この楽観論は、単なる技術への無関心ではなく、日本社会の根深い特性に基づいていると分析できます。
#### 1. 終身雇用と企業内での配置転換
日本の主要企業では、いまだに**終身雇用**の慣行が強く残っています。AIによって特定の業務が自動化されたとしても、従業員は解雇されるのではなく、企業内で新たな部署や職種に**配置転換**される可能性が高いという認識があります。この「企業が雇用を守る」という信頼感が、失業への懸念を和らげていると考えられます。
#### 2. AIを「代替」ではなく「支援」と捉える傾向
多くの日本企業では、AIを人間の仕事を完全に代替するものではなく、**業務効率を向上させるためのツール**として捉える傾向が強いです。AIは、ルーティンワークやデータ処理を担い、人間はより創造的で複雑な判断を伴う業務に集中するという「**協働モデル**」への期待が、失業の恐怖を上回っている可能性があります。
#### 3. 労働人口減少と人手不足
日本は深刻な**労働人口の減少**に直面しており、多くの産業で人手不足が常態化しています。この状況下では、AIによる自動化は「失業」ではなく、「**不足する労働力を補完する手段**」として歓迎される側面が大きいです。AIが担う業務が増えることで、むしろ残業の削減や生産性の向上が期待されています。
## まとめ:AI時代における日本の雇用モデルの試金石
日本のビジネスパーソンがAIによる失業を恐れないという事実は、日本の雇用モデルが、AIという巨大な技術変革の波に対して、ある種の**レジリエンス(回復力)**を持っていることを示唆しています。しかし、この楽観論が、AI時代に適応するためのスキルアップやキャリア再構築の遅れにつながるリスクも指摘されています。今後、日本社会がこの楽観論を維持しつつ、国際競争力を高めていけるかどうかが、大きな試金石となるでしょう。
—
**元記事のアンカーリンク:**
[元記事を読む](https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03079/102300022/)







